解体業者の資格一覧!信頼できる業者はどんな資格を保有しているの?
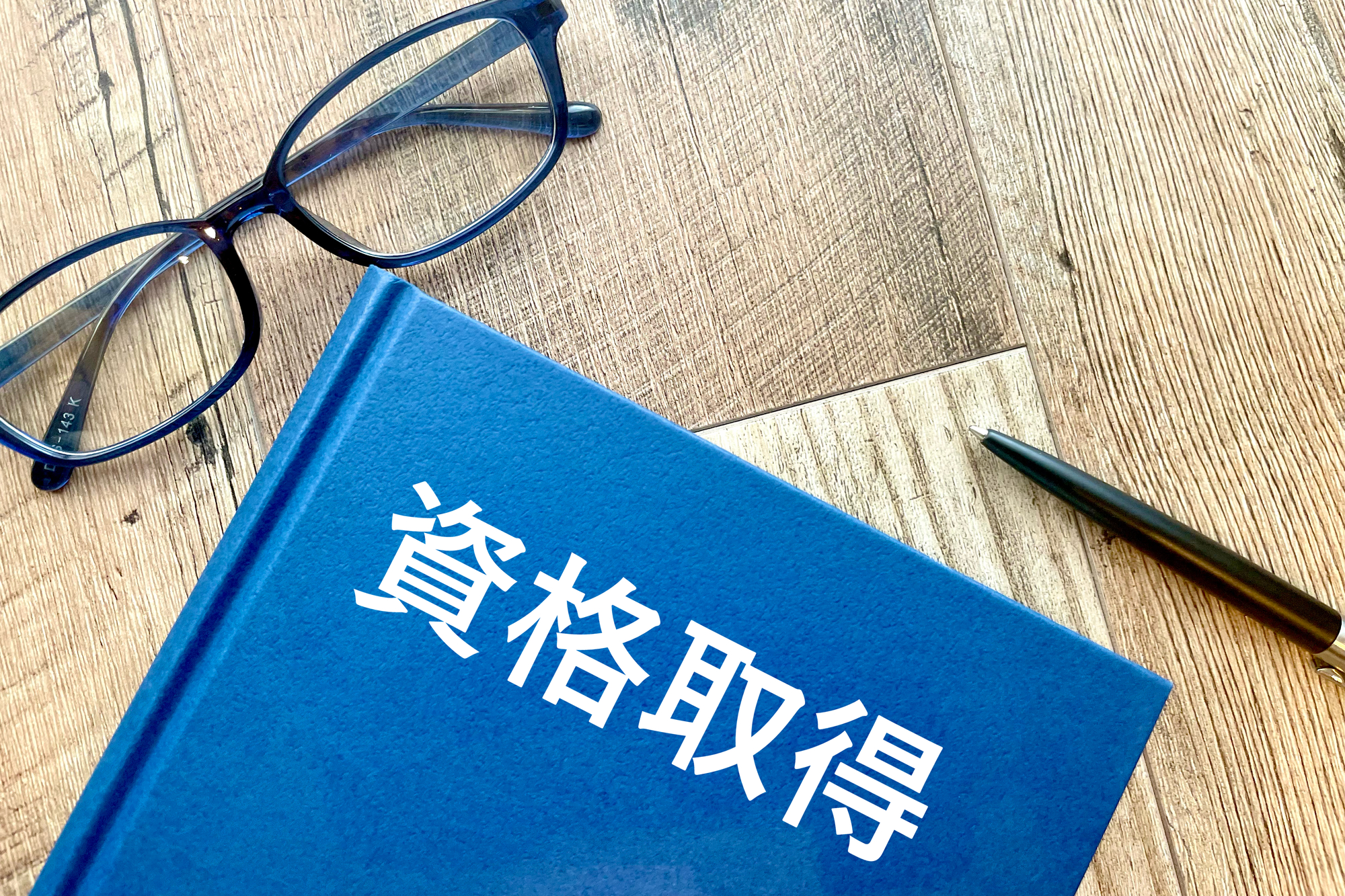
解体工事を依頼したいけれど、本当に信頼できるのかを見極めたいという方は、資格を保有しているかどうかを確認してみることをおすすめします。
一般的に解体工事業登録や建設業許可を取得していれば、信頼できる業者と周知されていますが、どのような資格を保有している技術管理者がいるかを把握すれば、解体業者の特徴を深く理解できます。
今回は解体工事業登録に関する資格を一覧にしてご紹介します。併せて、解体業者が受講すべき講習までご紹介しているため、安心して任せられる業者かどうかの判断にお役立てください。
解体工事業登録とは

解体工事業登録とは、建物や工作物の解体工事を請け負う際に必要な登録番号です。
2001年5月から解体工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事業登録の制度が開始されました。(1)建物を壊して更地にする(2)スケルトン工事をして内装を変えるなどの請負工事を行う場合には解体工事業登録が必要となります。
解体工事業登録と建設業許可の違い
| 解体工事業登録 | 建設業許可 | |
| 請負金額 | 500万円未満 | 500万円以上 |
| 取得要件 | ①技術管理者が在籍している ②技術管理者が不適格要件に該当しない | ①経営5年以上の役職者がいる ②自己資金500万円以上 ③専任技術者が常勤している ④不正行為がない ⑤役職者が欠格要件に該当しない |
解体工事を請け負える許可証には「解体工事業登録番号」と「建設業許可番号」があります。
建設業許可は取得要件のハードルが高くなりますが、500万円以上の解体工事を請け負うことができます。つまり、どのような許可を取得しているかを確認すれば、住宅の解体を中心に行っているのか、大規模解体を中心に行っているかを把握することも可能です。
解体工事業登録や建設業許可の必要性について詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。
関連記事:『解体工事には免許がいる?プロが良い業者の見極め方や注意点を解説』
解体工事業登録に必要な資格

解体工事業登録を取得するためには、技術管理者の在籍していることが前提条件です。そのため、次の資格保有資格者を在籍させる必要があります。どのような資格保有者が在籍しているかで、解体業者の特徴を把握できるため、資格について理解しておきましょう。
1級・2級建設機械施工技師
建設機械施工技師は、ブルドーザーや油圧ショベル、モータ・グレーダー、アスファルト・フィニッシャー、ブルドーザー、アースオーガの重機を扱うための国家資格です。施工管理業務、重機の取り扱い、検査が試験問題です。
2級は合格した重機しか取り扱えませんが、1級に合格すれば全ての重機を取り扱えるようになります。建設機械施工技師が在籍している解体業者に依頼すれば、現場の状況に応じた重機で騒音・振動・粉じんなどの影響を最小限に抑えた解体工事が期待できます。
解体工事の重機について詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。
関連記事:『解体重機のアタッチメントの種類まとめ!作業例や必要な資格まで解説』
1級・2級土木施工管理技士
土木施工管理技士は、土木工事(道路、橋、トンネル、ダム、河川、港湾、空港、鉄道など、社会インフラを整備するための工事)の施工管理・品質管理・安全管理が行えることを証明する国家試験です。
2級は「土木」「薬液注入」「構造物塗装」の中で合格した分野の施工管理が行え、1級に合格すれば、全ての分野の施工管理が行えるようになります。土木施工管理技士が在籍している解体業者に依頼すれば、公共性の高い解体工事も安心してお任せできます。
1級・2級建築施工管理技士
建築施工管理技士は、建設現場の施工計画、工程管理、品質管理、安全管理、関係者との打ち合わせなど、工事をとりまとめる能力を証明する国家試験です。
2級に合格すると主任技術者になれて外注総額税込4000万円未満の現場に配置され、1級に合格すると主任技術者・監理技術者になれて外注総額の上限なく現場に配置されます。
建築施工管理技士が在籍する解体業者に依頼すると、新築工事を想定して解体工事を行ってもらえます。
1級・2級建築士
建築士は建物の設計や工事監理に関わるための国家試験です。1級と2級で設計できる建築物の規模が異なります。2級は木造建造物と一定規模の鉄筋コンクリートや鉄骨の建造物の設計ができ、1級はあらゆる建造物の設計ができます。
建築士が在籍している解体業者は、解体後の土地活用などのノウハウを持っているケースが多いです。
1級・2級とび工(とび技能士)
とび工(とび技能士)は、鳶職人の技術レベルを示す国家資格です。「仮説の組み立て」「切削」「躯体工事」「重量物の運搬方法」「建物の解体」「建物の種類及び特徴」「安全衛生」などの知識があるかどうかを証明するものです。
2級より1級の方が高度な知識を保有していることを証明しています。とび工(とび技能士)が在籍している解体業者に依頼すれば、狭小地などでも足場を速やかに設置してもらえたり、スムーズに工事を進めてもらえます。
解体工事業者が受講すべき講習

解体工事業者は特定の作業をするために指定の講習を受講しなければなりません。そのため、「特定の作業とは何か?」「どのような講習を受講すべきか」を把握しておきましょう。
建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
建築物の骨組みで金属製の部材で構成される5m以上のものの組み立て、解体、変更を行う場合は、建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した人を作業主任者として選任し従事させなければなりません。
建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習では、鉄骨の構造や作業リスク、墜落・転落防止対策などについて学びます。そのため、講習を修了した人がいる解体業者に依頼すれば、鉄骨造の建物を解体する際に事故が起きにくい、安全性が高い工事が期待できます。
足場の組立て等作業主任者技能講習
高さが5m以上の足場の組立て、解体、または変更を行う際には、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、作業を行わせなければなりません。
足場の組立て等作業主任者技能講習では、足場作業の知識、工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 、作業者の教育について学びます。そのため、講習を修了した人がいる解体業者に依頼すれば、スムーズな仮設工事が期待できます。
足場の組み立てについて詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。
関連記事:『家の解体工事に足場はいるの?種類や必要な資格・許可をプロが解説!』
車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転
機体質量3t以上の車両系建設機械(整地用)を運転する場合は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了しなければいけません。これは労働安全衛生法に基づいたルールです。ドラグ・ショベルやホイールローダ、ブルドーザーで解体作業をする際は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了しているのかどうかを確認してみてください。
整地について詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。
関連記事:『整地とは?更地や造成の違いから仕上げ方法まで徹底解説』
車両系建設機械(解体用)の運転
機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)を運転する場合は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了しなければいけません。これは労働安全衛生法に基づいたルールです。ブレーカーやコンクリート圧砕機、解体用つかみ機、鉄骨切断機で解体作業をする際は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了しているのかどうかを確認してみてください。
アスベスト建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育
石綿(アスベスト)の撤去工事は、石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康被害を及ぼす恐れがあるため、アスベスト建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育を受けた人でなければ行えません。
講習では、石綿の有害性や石綿等の使用状況、保護具の使用方法、その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項を学びます。石綿(アスベスト)の撤去は大変危険なため、事故を防ぐためにも講習を受講したのかどうか確認しておくことをおすすめします。
石綿(アスベスト)の撤去工事について詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。
関連記事:『アスベスト解体工事の手順は?危険レベル別の除去方法や注意点も解説』
関連記事:『アスベストの解体費用相場は?場所別の目安や安くするコツも紹介』
関連記事:『アスベスト調査義務化とは?費用はどちら負担になるの?』
関連記事:『【画像あり】アスベストを見分ける7つの方法と注意点を深掘り解説』
安全衛生責任者教育
建設現場で労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を守る役割を担います。そのため、職長は安全衛生責任者教育を受けなければなりません。これは、安全衛生法に基づくルールです。講習では、作業方法や作業員の配置方法、監督方法、異常事態時の措置などについて学びます。
解体現場で事故が起きると大変な事態となるため、講習を受講したのかどうかを確認しておくことをおすすめします。
玉掛け技能講習
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置による玉掛作業に従事する場合には、玉掛け技能講習を修了しなければなりません。講習ではクレーン等、玉掛け作業を学びます。重量物の移動や撤去作業が安全に行われるかどうか気になる方は、講習を受講したのかどうかを確認しておくことをおすすめします。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体を行う場合は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習を修了した人を選任者に選び従事させる必要があります。
講習では、コンクリート造の特徴、解体手順、必要な重機の選定、安全対策、作業員への指導方法などを学びます。コンクリート造の解体の品質にも影響するため、依頼する場合は講習を受講したのかどうかを確認しておきましょう。
コンクリート造の解体について詳しく知りたい方は、下記の記事をお読みください。
関連記事:『コンクリート解体の単価相場は?土間/駐車場/RC費用と安くするコツ』
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
軒高5m以上の木造建築物の解体を行う場合は、木造建築物の工作物の解体等作業主任者講習を修了した人を選任者に選び従事させる必要があります。
講習では、木造建築物の特徴、解体手順、必要な重機の選定、安全対策、作業員への指導方法などを学びます。木造建築物の解体の品質にも影響するため、依頼する場合は講習を受講したのかどうかを確認しておきましょう。
今回は体業者の特徴を深く理解できるように、関連の資格と講習をご紹介しました。しかし、信頼できる解体業者かどうかは別の方法でも見極めることが可能です。優良な解体業者の見極め方や探し方について詳しく知りたい方は、次の記事も併せてお読みください。
関連記事:『優良解体業者の11個の特徴!依頼する際に費用を抑えるコツまで解説』
関連記事:『【日本全国版】解体工事業者ランキング!Google口コミ高評価を厳選』
まとめ
解体工事を請け負う際には解体工事業登録(または建設業許可)が必要です。解体工事業登録の取得要件として、①技術管理者が在籍している②技術管理者が不適格要件に該当しないことを満たさなければなりません。つまり、技術管理者が在籍していることが前提条件です。
技術管理者になるための資格には、建設機械施工技師や土木施工管理技士、建築施工管理技士、建築士など、さまざまなものがあります。どのような資格を保有しているか聞くことで、どのような知識を持っていて、どのような作業が得意なのか把握することが可能です。
一般的には、解体工事業登録(または建設業許可)を取得していれば、信頼できる業者と言われています。しかし、より深く調べたいという方は「どのような資格を保有しているのか?」「どのような講習を修了しているのか?」を聞いてみるとよいでしょう。
上池解体興業(ボッコス)は見積依頼を無料で受け付けています。その際に、どのような資格を保有しているのか尋ねて頂いて構いません。ぜひ、気になる方はご質問ください。
千葉・埼玉・神奈川・東京の住宅解体
会社名:株式会社 上池解体興業(ボッコス/BOCCOS)
住所:〒152-0002 東京都目黒区目黒本町6-9-18
TEL:03-6846-5035
営業時間・定休日:9:00~18:00 土日祝
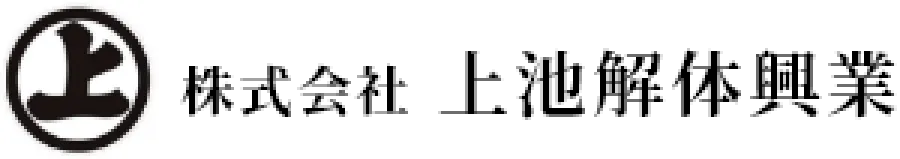
 法人の方へ
法人の方へ