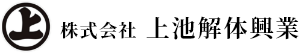【お家解体ガイド】工事で必要な手続き・届出をプロがわかりやすく解説

解体工事は多くの人にとって初めてのことばかりで、手続きについてよくわからない…という方も多いでしょう。
この記事では「解体工事はどんな手続きが必要?」「手続きを忘れるとどうなるの?」
といったお悩みを解決するため、解体工事のプロである株式会社上池解体興業が、解体工事の手続き・流れをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、スムーズに準備を進められますよ。
手続きを怠ると罰則を科されるおそれもあるため、よく読んでおきましょう。
解体工事で手続きを怠るとどうなる?

家の解体工事でもっとも重要なポイントは、必要な書類の提出を怠らないことです。
では、手続きを怠ってしまった場合どうなるのか、みてみましょう。
書類の提出を怠ると罰則を科される
解体工事届出と建物滅失登記申請書は、解体工事の依頼主による提出が義務付けられています。
提出しないと以下のような罰金を科されることがあります。
- ・解体工事届出:最大20万円
- ・建物滅失登記申請書:最大10万円
解体工事届出と建物滅失登記申請書は、業者による代行提出も可能です。
ただし、手数料を請求されることがあるため、見積もりを確認しておきましょう。
解体費用相場について解説した記事もあります。
→家の解体費用の相場は?安く抑えるコツと知らなきゃ損する注意点も | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)
解体後は固定資産税が上がるって本当?

家屋を解体すれば、建物にかかっていた固定資産税はかからなくなります。ただし、固定資産税が安くなるとは限りません。なぜなら、軽減特例の対象外になるからです。
建物がある土地は、固定資産税が1/3~1/6に軽減されています。
そのため解体によって建物がなくなると、固定資産税が軽減されなくなります。
すると、土地にかかる固定資産税が増え、税金の負担は大きくなってしまうのです。
固定資産税への対策としては、建て替えや土地の売却などが有効です。
まずは解体工事業者を探そう!

解体工事の手続きには、さまざまな書類の届け出が必要であり、作成には専門知識が必要です。そのため、解体工事がはじめての方には難しいことも多いです。まずは専門業者に相談しましょう。
解体工事のプロに相談することで、解体工事の前に必要な耐震診断やアスベスト調査などもまとめて一括で依頼できます。施工前の調査は補助金申請などの際に重要になるため、専門家に相談のうえ欠かさず行っておきまましょう。
インターネットなどで解体業者のサイトを見ると、対象となる建物の規模に応じた解体を行っているか、どのようなサービスをしてくれるのかが書いてありますので、比較して自身に合った業者を選んでくださいね。
解体業者の選び方を解説した記事もあります。
→家の解体業者の損しない選び方!トラブルを避ける方法も解説 | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)
解体工事前にやるべき手続きは3つ

解体工事は、施工前の準備が肝心です。次の3つを忘れずに行いましょう。
- 1.解体工事届出をする
- 2.道路使用許可書の提出
- 3.工事に使用しないライフライン停止
1.解体工事届出をする
建築リサイクル法にもとづき、解体工事の7日前までに解体工事届出を申請する必要があります。建築リサイクル法とは、解体工事において資材の分別・リサイクルを義務付けた法律です。80平方メートル以上の住宅の解体工事では、解体工事届出が必要になります。
解体工事に関する書類の提出・手続きは、依頼主の義務です。怠ると罰金を科されることがあるため注意しましょう。解体工事届出は、専門業者による代行も可能で、その場合は施主は委任状を書くだけで届出が完了します。
2.道路使用許可書の提出
解体工事では、作業用車両が敷地外に停車するため、道路使用許可申請が必要です。許可を受けずに工事を行うと、道路交通法違反になります。
とはいえ、道路使用許可申請の義務は施工業者にあるため、業者が済ませてくれていることも多いです。ただし委任する場合、施工費用に手数料が含まれていることがあるので、見積もりを確認しておきましょう。
解体工事費用を節約したいという方は、自分で管轄の警察署に行き、申請することも可能。申請書類はインターネットで警察署ホームページを調べるとダウンロードページが見つかるはずです。
3.工事に使用しないライフライン停止
ガスや電気が通ったまま解体工事をすると、火災などの事故につながります。そのため、施工までに各機関へ問い合わせて、ライフラインを止めておきましょう。余裕を持って連絡しておくことがおすすめです。
停止するために立ち合いが必要なケースもあるため、事前に電話などで確認しておくと良いですよ。
ただし、水道は解体工事で使用することがあります。施工業者と相談のうえ、必要であれば残しておきましょう。
解体工事を安心・安全に進めるためにやっておこう!

解体工事を行ううえで必要なことは、手続きだけではありません。
なにか問題が起きれば、着工の開始が遅れ、余計な費用は発生してしまう可能性があります。解体工事を安心して進めるために、以下のことを必ずやっておきましょう。
私物の回収・処分
家に残った私物は、施工までに回収しておきましょう。不要な家具・家電などが残っていると、処分費用を請求されることがあります。不要なものは自ら処分するか、リサイクルすることで施工費用を抑えられます。施工費用の足しにするために売却するのもおすすめです。
近隣住民への挨拶・説明
解体工事では、騒音や振動、ホコリなどトラブルの原因になる要素が多いです。そのため、施工前に近隣住民へ挨拶・工事の案内をしておきましょう。個別挨拶や住民説明会、掲示による周知などが必要です。
近隣への挨拶はマナーとしてだけでなく、義務付けている自治体もあります。たとえば東京都目黒区では、次のようなルールがあります。
- ・標識設置:施工の15日前まで
- ・近隣住民への説明:施工の7日前まで
- ・説明会報告書の提出:施工の3日前まで
自治体によって近隣挨拶のルールが定められているので、確認しておきましょう。近隣挨拶は専門業者による代行も可能です。
家の解体工事前の挨拶に粗品は必要?失敗しない7つの品物を紹介! | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)
解体工事後に必要な3つの手続き

解体工事後は、こちらの3つの手続きが必要です。
期限が決められているものあるため、計画を立てて実行することがおすすめ。
- 1.建物滅失登記申請の提出
- 2.工事に使用したライフラインの停止
- 3.固定資産税に関する手続き
解体工事前の手続きと同様に、怠ると罰則を科されることがあるため注意しましょう。
1.建物滅失登記申請書の提出
解体工事から1か月以内に建物滅失登記申請書を提出しましょう。
建物滅失登記申請書とは、建物がなくなったことを報告する書類です。手続きを怠ると存在しない建物に固定資産税がかかったり、罰金を科されたりしてしまいます。
建物滅失登記申請書の提出は、所有者の義務です。施工業者に代行してもらう場合でも、委任状の作成が必要です。
2.工事に使用したライフラインの停止
解体工事では、粉じんの飛散を軽減するために水を撒きながら作業します。そのため、施工が終わるまで停止手続きはできません。施工が終わり次第、水道局へ連絡して水道を止めてもらいましょう。
また、施工に使用する水道代を業者が負担してくれるかどうか確認しておくことも大切です。
3.固定資産税に関する手続き
家屋を解体することで、その建物に対する固定資産税がかからなくなります。一般的に、法務局に建物滅失登記申請書を提出することで自治体に通知が届くため、別途手続きは必要ありません。書類の不備などの連絡があれば、指示に従って手続きを進めましょう。
ただし、解体後も土地に対する固定資産税はかかります。固定資産税をカットするためには、土地の売却などの対策が必要です。
解体する家の所有者が亡くなっているときは?

建物の所有者が亡くなっている場合は、通常の手続きに加えていくつかの準備が必要になります。ここからは、故人宅の手続きについて詳しく解説します。
名義人を確認する
まずはその建物の名義人を確認しましょう。住宅の名義人は、今まで住んでいた方だとは限りません。「父のだと思っていたら祖父のままだった」というケースも多いです。名義人が違えば、相続などの手続きも一からやり直しになってしまうので、最初に確認しておくことが大切です。
相続関係の手続き
故人宅の解体工事では、主に相続人が手続きをします。そのためまずは、法定相続人による協議を行い、建物の相続人を確定させましょう。
相続の話し合いは数か月以上かかることがあります。年度をまたいでしまうと税金の計算や解体工事の補助金申請などに影響が及ぶため、早めに協議をはじめるのがおすすめです。
相続人が解体工事の手続きをする
基本的には、故人宅の名義を相続人に変更してから解体工事の手続きを進めます。しかし相続してすぐに解体する場合は、名義変更せずに故人名義のまま手続きできることがあります。その場合、相続人であることを証明する遺産分割協議などの提出が必要です。
そのほかの手続きは、通常通りです。解体工事届出や道路使用許可申請書を提出して解体工事を行いましょう。
解体する家にアスベストが含まれていたら?

古い家の解体では、建築資材にアスベストが含まれている可能性があります。
アスベストは吸い込むと重大な健康被害を引き起こすリスクがあり、所定の手順を踏んで解体に臨む必要があります。
アスベストを解体する際には、事前に行う届出手続きがいくつかあり、「特定粉じん排出等作業届書」と「事前届出」は発注者である施主が提出の義務者です。
提出手続きは業者に委任することができるため、特にアスベスト解体工事が初めての方はプロにお任せすると良いでしょう。詳しくは、以下の記事で解説しています。
→アスベスト解体工事の手順は?危険レベル別の除去方法や注意点も解説 | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)
解体工事後に考えるべきこと

解体工事が終わったあとも、考えるべきことはあります。
土地をどうするのかによっては、必要な手続きが変わりますので、早めに利用方法を検討しましょう。
1.今後の土地利用方法を考えよう
前述したとおり、建物がなくなることで固定資産税が高くなり、土地を所有しつづけるかぎり払っていく義務があります。
したがって早めに土地の利用を考えましょう。
- ・駐車場にして副収入を得る
- ・売却する
- ・資材置き場として貸し出す
- ・家を建てて住む
といった方法が考えられます。
また近年は「コインランドリー」「太陽光発電システムの設置」「トランクルーム(貸倉庫)」も人気です。親族など関係者とよく話し合い、周辺環境のことも考えながら決めていきましょう。
2.土地のメンテナンスをしよう
解体後の更地を放置すると、害虫や雑草などによって荒れてしまいます。荒れた土地は近隣住民とのトラブルの原因になるだけでなく、将来の建築時の施工費用が高くなることもあります。そのため、コンクリート舗装などの整地がおすすめです。整地をすることで売却時の評価額が高まることもあります。
解体後すぐに建て替えや売却をしない場合には、土地の管理方法について考えておきましょう。
まとめ
解体工事に必要な手続きと注意点を解説しました。
解体工事では、さまざまな手続きが必要です。特に解体工事届出などは依頼主に義務があり、怠ると罰金を科されることがあります。知識のない方がすべて一人で進めるのは難しいため、専門業者への依頼がおすすめです。
株式会社上池解体興業(BOCCOS/ボッコス)は、お客さまの負担を最低限に抑えるサポートをしております。解体工事や手続きへの不安など、わからないことは何でもご相談ください。当社は、現地調査や見積もりを無料で行っております。まずは相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
千葉・埼玉・神奈川・東京の住宅解体
会社名:株式会社 上池解体興業(ボッコス/BOCCOS)
住所:〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-6-22
TEL:03-6846-5035
営業時間・定休日:9:00~18:00 日曜日