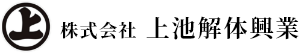住宅解体工事に必要な届出は5つ!相続やアスベストの手続きも解説!

住宅の解体をするうえで悩みの種は届け出です。
「住宅解体にはどんな届出が必要?」「必要な書類や提出方法は?」
結論からいうと、住宅解体工事では4つ以上の届出が必要であり、怠ると罰金を科されることもあります。
本記事では、家を解体するときに必要となる手続きや届出、忘れた場合の対処法などをわかりやすく解説します。
また「亡くなった方の家を解体する場合」「アスベストが含まれる家の場合」もケース別に紹介。
はじめての解体工事を検討している方でもわかりやすいように、解体のプロである株式会社上池解体興業が専門用語の説明をふくめながら解説するので、安心して読んでみてください。
解体の流れはこちら「家を壊す費用や流れは?解体工事に必要な情報をプロがひと通り紹介 | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)」
住宅解体で必要な5つの届出

家屋の解体では、5つの届出が必要です。
- ・解体工事届出
- ・道路使用許可申請
- ・近隣説明会報告書
- ・ライフラインの停止
- ・建物滅失登記申請
とくに解体工事届出と建物滅失登記申請は施主の義務であり、提出しないと罰則もあるため注意しましょう。
1.解体工事届出
対象:80㎡以上(約24坪)の家屋
提出日:解体工事開始の7日前まで
提出先:各自治体の関連部署(建築課、環境課等)
忘れた場合:20万円の罰金
建築リサイクル法にもとづき、80㎡以上の住宅解体では、「解体工事届出」が必要です。
解体工事開始の7日前までに自治体に提出しましょう。
手続きに必要な書類
- ・届出書
- ・分解解体等の計画
- ・案内図
- ・設計図または写真
- ・工程表
- ・委任状(業者に委任する場合)
解体工事届出は、建築リサイクル法という法律によって施主に義務づけられており、提出しないと20万円の罰金対象となります。委任状があれば業者による代行も可能なので、書類の作成・提出に不安がある方は業者にまかせましょう。ただし、手数料がかかることもあるため要注意。
2.道路使用許可申請
対象:敷地が狭いなど、道路に工事車両を停める場合
提出日:工事の14日前まで
提出先:管轄の警察署
忘れた場合:道路交通法違反として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
解体工事では、重機やトラックが敷地外の道路に停まるため、「道路使用許可申請」が必要です。また、足場が敷地外に出るなど継続的に道路を使用するのであれば、「道路占用許可申請」もあわせて必要です。
手続きに必要な書類
- ・道路許可申請書(2通)
- ・道路使用の場所、方法等を明らかにした図面
- ・道路使用の方法や形態等を補足するための書類(公安委員会が必要と認めた場合)
道路使用許可申請は、工事の14日前までに地域の警察署に提出します。申請しないと道路交通法違反として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を科されることも。ただし、道路使用許可申請の義務は、解体業者にあります。施主がすることはないものの、手数料がかかることもあるため、見積もりをチェックしておきましょう。
3.近隣説明会報告書
対象:工事前の近隣住民への説明を義務づけている自治体
提出日:工事が始まるまで
提出先:自治体による
忘れた場合:自治体による
解体工事は、騒音や振動など近隣への影響が大きいです。トラブルにならないためには、事前の説明が欠かせません。近隣への説明方法は、3つのパターンがあります。
- ・個別説明
- ・住民説明会
- ・提示
ただし、近隣説明のルールは自治体によってさまざまです。たとえば東京都目黒区では、7日前までに近隣住民への説明(工事内容・アスベスト調査結果など)、3日前までに近隣説明報告書の提出が必要です。
住民説明は専門知識が必要なため、基本的には業者が代行してくれます。ただし、施主も顔を出しておくことで、近隣からの反感を買いにくくなるでしょう。
こちらの記事も参考に→「家の解体工事前の挨拶に粗品は必要?失敗しない7つの品物を紹介! | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)」
4.ライフラインの停止
取り壊しをする家のライフラインを停止しておく必要があります。
- ・電気
- ・ガス
- ・電話
- ・インターネット回線
- ・ケーブルテレビ
電気はアンペアブレーカー、メーター、引き込み線などの撤去作業が必要なため、解体工事の2週間前までに手続きをしましょう。またガス会社では立ち合いが必要なケースもあるため、余裕をもって停止の連絡をすると良いです。
水道は解体工事で使うため、解体工事後に停止手続きをします。
こちらの記事も参考に→「家の解体工事で電気や水道は止めるべき?手続きのタイミングと流れ | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)」
「家の解体工事で電話線は取り外すべき?手続きの流れや注意点まで解説 | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)」
5.建物滅失登記申請
対象:すべての住宅解体
提出日:解体後1か月以内
提出先:法務局
忘れた場合:10万円以下の罰金
「建物滅失登記申請」とは、建物がなくなったことを国に報告する書類です。建物滅失登記の義務は施主にあり、解体後1か月以内に法務局への提出が必要です。提出しないと10万円以下の罰金を科されるため、早めに済ませておきましょう。土地家屋調査士への委任も可能です。
手続きに必要な書類
- ・滅失登記申請書
- ・請負業者が作成する建物滅失証明書
- ・請負業者証明書と業者の印鑑証明
- ・取り壊した家の登記簿や図面
建物滅失登記申請によって「建物がない土地」になることで、固定資産税の計算方法も変わります。税金のむだを抑えるためにも、必ず確認しておきましょう。
固定資産税は1月1日時点で計算されるため、年末に取り壊して年明けに建物滅失登記申請をする場合は役所の窓口に相談しましょう。基本的には、提出が遅れても12月31日以前に取り壊したのであれば、翌年度以降は建物への固定資産税がかかりません。
故人宅の住宅解体に必要な届出

亡くなった方の住宅の解体を相続人が行う場合、本人による解体とは手続きが異なります。
- 1.名義人の確認
- 2.抵当権の有無を確認
- 3.解体工事
- 4.相続関係の書類とともに建物滅失登記
1.名義人の確認
前提として、解体工事の依頼は未相続でもできます。ただし、解体工事後の建物滅失登記申請は、相続人しかできません。所有者や法定相続人の確認をしましょう。
建物滅失登記は1か月以内に提出が必要になるため、相続の話し合いを終えてから解体工事に進むのが一般的です。
2.抵当権の有無を確認
抵当権とは、住宅ローンを利用する際に、金融機関が建物を担保にする権利のこと。
抵当権を外さなければ解体できませんが、住宅ローン返済中の建物は抵当権を外せません。住宅ローン完済していない場合はローンの支払いを終え、金融機関に建物滅失に関する同意書を作成してもらう必要があるため要注意です。
3.解体工事
解体工事を行う前に、建物の法定相続人同士で話し合い、「解体を行うかどうか」「費用の負担割合はどうするか」などを決める必要があります。建物滅失登記申請を行う際に「遺産分割協議書」を提出することもあるため、作成しておくと良いでしょう。
4.相続関係の書類とともに建物滅失登記
故人宅の建物滅失登記では、相続人であることを証明するために、故人と相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書の提出が必要です。解体工事に進む前に、遺産分割協議などで相続人であることを確認しましょう。
通常の手続きに加え、必要となる書類
- ・亡くなられた所有者の戸籍謄本または除籍謄本
- ・亡くなられた所有者の住民票または戸籍の附表(建物の住所と現在の住所が異なる場合)
- ・相続人の戸籍謄本
また、相続から解体工事まで数か月以上かかる場合は、相続登記による名義変更がおすすめです。名義人がいない状態が続くと、誰の建物なのかがあやふやになり、権利関係が複雑になってしまいます。自分が相続した建物だと証明するためには、相続登記が必要です。
こちらも参考に→「実家解体を後悔しない!気持ちよく進める方法やお祓いの必要性を解説 | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)」
アスベストをふくむ住宅解体工事に必要な5つの届出

アスベストをふくむ住宅の解体工事は、通常の届出にくわえて5つの書類が必要です。
- ・事前調査報告書
- ・工事計画届出
- ・建物解体等作業届出
- ・特定粉じん排出等作業の実施届出
- ・飛散防止方法等計画の届出
アスベストとは、住宅資材にふくまれる繊維状鉱物で、吸引すると肺がんなどにつながる有害な物質です。アスベストの使用が禁止される2006年以前に建てられた住宅には、アスベストがふくまれていることも。
アスベストは摩擦などによって飛んでしまうので、解体工事前の調査が義務づけられています。アスベスト調査の結果は、1~3の「レベル」で表され、1がもっとも危険な状態です。
1.事前調査報告書
2022年4月1日から、解体工事前のアスベスト調査が義務化されました。これにともない、解体部分の床面積がのべ80㎡以上あるいは施工費用100万円以上の工事では、自治体への調査結果報告が必要になりました。
解体工事前のアスベスト調査は、解体業者から調査会社に依頼するのが一般的。調査内容を解体業者および施主が確認して、石綿事前調査結果報告システムにて自治体に提出します。
調査によってレベル1~3と診断された場合は、アスベスト撤去のルールにもとづいた解体工事が必要であり、下記2~4の届出が必要になります。
2.工事計画届出
もっとも危険なレベル1の解体工事では、労働安全衛生法にもとづき工事計画届出が必要です。
工事計画届出とは、工程表や図面などとともに「このような計画で工事を進めます」という報告をする書類です。リスクの高い工事になるため、工程などから第三者のチェックを入れて作業員や近隣住民の安全を守ります。
工事計画届出は工事の規模を問わず、14日前までに解体業者が労働基準監督署に提出します。
3.建物解体等作業届出
レベル1とレベル2の建物の解体工事では、石綿障害予防規則にもとづき、「建物解体等作業届出」が必要です。着工までに解体業者が労働基準監督署に提出します。
また、アスベストをふくまない解体工事同様に、建築リサイクル法にしたがって解体工事届出も必要です。解体工事届出は、工事の7日前までに自治体への提出が必要であり、建物解体等作業届出とは期限や提出先が異なるため注意しましょう。
4.特定粉じん排出等作業の実施届出
アスベスト飛散防止のための作業基準は、大気汚染防止法にも記載されています。
そのため、レベル1とレベル2の解体工事では、大気汚染防止法にもとづく「特定粉じん排出等作業実施届出書」が必要です。特定粉じん排出等作業実施届出書は、工事の14日前までに解体業者が自治体に提出します。
5.飛散防止方法等計画の届出
大気汚染防止法にもとづく特定粉じん排出等作業実施届出書の必要要件を満たしており、次の要件のいずれかにあてはまる建物は、環境確保条例にもとづく「石綿飛散防止方法等計画届出書」も必要です。
- ・アスベストをふくむ吹付け材の面積が15㎡以上
- ・建物ののべ面積が500㎡以上
一軒家の面積は約100㎡ほどなので、一般住宅の場合は主に1つ目の吹付け材の面積がポイントになります。要件にあてはまる建物は、工事の14日前までに自治体への届出が必要です。
アスベスト解体についてはこちらも参考にしてください。
「アスベスト解体工事の手順は?危険レベル別の除去方法や注意点も解説 | 株式会社上池解体興業 (kamiike-kaitai.com)」
まとめ
住宅解体工事では、さまざまな届出が必要となります。
とくに解体工事届出と建物滅失登記申請は施主に義務があり、提出しないと罰金を科されるため注意しましょう。
解体工事の届出は、建物や場所によって必要な書類が異なり、期限や提出先も変わります。書類の作成には専門知識も必要になるため、はじめての方ではわからないことが多いでしょう。そのため、書類の作成方法や業者による届出についてくわしく説明してくれる業者がおすすめです。
株式会社上池解体興業(BOCCOS/ボッコス)では、お客さまとのコミュニケーションを大事にしており、書類作成も徹底的にサポートしております。解体工事を検討している方は、気軽にお電話ください。
千葉・埼玉・神奈川・東京の住宅解体
会社名:株式会社 上池解体興業(ボッコス/BOCCOS)
住所:〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-6-22
TEL:03-6846-5035
営業時間・定休日:9:00~18:00 日曜日