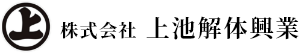住宅解体の手順を紹介!工事の全体像をしっかり把握しよう

解体工事は、頻繁に経験する工事ではありません。人生でも一度きりという方も多いでしょう。
「解体工事ってどんな流れで進むんだろう」と、どのように工事が進んでいくのかイメージできない方も多いと思います。
この記事では、住宅解体の手順をわかりやすく解説。たくさんのお客さまをサポートしてきた株式会社上池解体興業が、はじめての方から相談されるポイントを中心に紹介します。
「解体工事を検討しているけど、イメージがつかめなくて困っている」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
住宅解体の大まかな手順・流れ

お問い合わせから工事までの流れは、以下の手順で進みます。
1.お問い合わせ
解体工事を依頼する業者を選び、電話・LINE・フォームなどからお問い合わせします。
まずは業者のホームページ等を参考にしながら、3〜5社ほど気になる業者をピックアップしましょう。
悪質業者にあたってしまう可能性もあるため、解体業者探しは、施主自身が行うことのなかでもっとも時間をかけるべき工程です。
対応の丁寧さや見積もりの明確さなどを比較してみましょう。わからないことがあればとにかく質問をして、対応を見るのもおすすめ。複数の業者の見積もりを比較してから決めたいと伝えて嫌な反応をされたら、その業者は避けるのがいいかもしれません。
関連記事:家の解体業者の損しない選び方!トラブルを避ける方法も解説
2.現地調査
現地調査では、解体する建物の規模や構造などを確認し、必要な施工を考えます。調査自体は半日程で終了します。
「ここは残してほしい」などの要望も、現地調査時に相談すると良いでしょう。
なお設備や埋設物の扱いについて相談が必要な場合に、「施主の立ち会い」が必要になるケースがあります。そのため問い合わせの際に、立ち会いが必要かどうかを確かめておくと良いでしょう。
3.見積もり
現地調査をもとに、見積もりを行います。ほとんどの解体業者では、無料で見積もりを行ってくれます。
複数の業者の見積もりを見比べて、施工内容や費用を明確にしてくれる業者を選びましょう。
業者選びで迷ったら、対応の丁寧さ・見積もりの明確さ・アフターケア(何かあったときの対応など)の有無などで比較するのがおすすめです。
業者との契約後は、施行日などの具体的な打ち合わせがあります。このあとの流れは業者によって多少異なるため、見積もり時や契約時にその後の流れを聞いておきましょう。疑問や不満を抱えたまま依頼すると、のちのちトラブルになるおそれがあります。
4.契約
見積もりに納得できたら契約となります。
施工日などの具体的な打ち合わせを行い、施工に向けて準備をスタートします。
施工についての不安や疑問などは施工までに解決しておきましょう。
5.官公庁へ書類提出
80平米以上の解体は、官公庁への届け出が必要です。
具体的には「解体工事届出」と「道路使用許可申請書」を提出しなければなりません。
ただし、解体業者が対応するため、お客さまは書類の確認と捺印のみで構いません。
関連記事:住宅解体工事に必要な届出は5つ!相続やアスベストの手続きも解説!
6.近隣へのご挨拶
解体工事では、騒音や粉塵など近隣への影響があります。
そのため事前に挨拶に伺い、トラブルを未然に防ぎます。
基本的に業者のほうで行いますが、挨拶回りの内容を知っておきたい場合や、自分でも挨拶回りをしたい場合には、業者に相談してみると良いでしょう。
7.解体工事開始
解体工事は、建物の規模・解体箇所・構造・周辺環境などによって工期が変わりますが、一般的には、1~2週間です。あらかじめ作成した施工スケジュールに沿って作業を進めていきます。
8.廃棄物の処理
解体によって生じた産業廃棄物は、適切な処理が必要です。
許可を受けた業者による処理が必要なため、解体業者が責任を持って処理いたします。
9.工事完了
解体後に産業廃棄物を撤去したら、土地を簡単に整備して解体工事完了です。
お客さまにご確認いただき、問題がなければお支払い、引き渡しになります。
住宅解体する前に行っておくべき手順もある

解体工事に入る前に、工事を依頼した施主にも、施工業者にも事前にやらなくてはいけないことがいくつかあります。
解体する住宅と近隣の調査
住宅解体の前には、耐震診断とアスベスト調査が必要です。耐震診断とは、古い住宅を現行の基準でチェックする調査で、点数が低い場合は改修・解体工事に補助金が支給されることも。
またアスベスト調査とは、人体に有害なアスベストという物質が含まれていないか確認する調査です。自治体によってはアスベスト調査や解体工事への補助金が支給されます。
一方で近隣住宅を対象とした家屋調査も欠かせません。家屋調査とは、工事前の近隣住宅の傾斜やキズなどを調査して記録しておくこと。家屋調査をしておくことで、「工事のせいでキズができた」というクレームを避けられます。
これらの調査は、基本的には解体業者が手配してくれます。手数料や調査費用が見積もりに含まれていることがあるので、確認しておきましょう。
関連記事:解体工事前の近隣家屋調査とは?調査項目や費用、流れを教えます
近隣挨拶・説明会
住宅解体工事では、振動などによって近隣住民に多少の迷惑をかけてしまいます。そのため、あらかじめ挨拶・説明にうかがいましょう。近隣への説明は、おもに次の3種類で行われます。
- ・個別説明
- ・近隣住民説明会
- ・スケジュールなどの提示
自治体によっては近隣挨拶へのルールが定められていることも。説明会報告書の提出などが必要になることがあるため注意しましょう。近隣挨拶は、解体業者が代行してくれることも多いです。
家の中の準備
解体工事の前に、私物を片付けておきましょう。家具や家電が残っていると撤去費用が割高になることがあります。
また、電気やガスなどのライフラインは、事故の原因になるため工事の前に止めておきましょう。工事のスケジュールに影響がでないように、早めに電気会社などへ連絡しておくのがおすすめです。ただし、水道は工事に使うため、止める必要はありません。
関連記事:解体する建物に残していいものはある?片付けるべきものや費用を解説
住宅解体する流れ・手順

解体工事は以下の手順で進んでいきます。
1.足場組み立て・養生シートの設置
2.室内の残置物撤去
3.屋根や瓦の撤去
4.手作業で窓ガラス等の内装材解体
5.重機を使って建物本体の解体
6.地中埋設物の確認と撤去
7.清掃と整地
1.足場組み立て・養生シートの設置(1日)
まずは足場の設置と養生の組み立て作業から始めます。
足場は高所作業のために必要なものです。また解体作業で発生する「ホコリやチリ、音」が外へ漏れたり、木屑等の破片が飛び散ったりするのを防ぐために建物全体をシートで覆います。
解体する家が大きい場合には足場の組み立て作業に時間がかかるため「2日以上」要する場合もありますが、一般的な2階建て木造住宅であれば「1日程度」で終了します。
関連記事:養生シートなしの解体工事は違法?対策方法を解体のプロが解説!
2.室内の残置物撤去
解体する家の中に家電や家具などの家財が残っている場合には、解体前に解体業者の方で撤去します。家財撤去は施主に「捨てて良いか」の確認を経ずに処理される場合が大半ですので、大切なものや売りたい不用品がある場合には、事前に片付けておきましょう。
3.屋根や瓦の撤去
基本的に、家の解体工事は屋根や瓦など上の方から取り壊していきます。
法律で分別解体が義務付けられていますので、材質ごとの区分けできるように手作業で瓦を1枚ずつ取り外します。そして瓦撤去後は、「ルーフィング」と呼ばれる屋根部分の下地を撤去。屋根部分は素材が異なる場合も多いため、きちんと分別をし「産業廃棄物」として処理します。
屋根の解体は手作業で進める手間があるため、「1〜2日程度」かかります。
スレート瓦(セメント瓦)の場合は、アスベストが含まれる場合がありますので、慎重な取り扱いが必要です。
4.手作業で窓ガラス等の内装材解体
屋根解体の次は、家屋内装部分の撤去に取り掛かります。
給湯器の設備や、建物の中の石膏ボード・土壁・窓ガラス。そして照明器具やドアなどを手作業で解体していきます。順番を間違えると屋根がくずれ落ちてしまうので、作業員は手順を踏んで確実に作業を行います。
内装解体後のガラスや木材などの廃材は、建設リサイクル法に従い分別します。
人力での解体作業と分別処理に時間がかかるため、「3日程度」必要です。
アスベストが使われていれば、適切に処理しなければなりません。
5.重機を使って建物本体の解体
屋根と内装の解体が終わったら、いよいよ建物本体の解体工程です。
通称ユンボと呼ばれる、先端にハサミがついた重機でまず柱や梁などの構造体を重機を使って解体します。通行人が多い場合は、交通誘導をするなどして近隣の安全を確保することもあります。
壁や床を取り壊し、そのあとに、基礎や土間の撤去を行います。
散水でホコリの飛散をおさえながら行い、建物本体の解体には「3〜7日」かかります。
6.地中埋設物の確認と撤去
建物の杭や大きな岩、廃材や浄化槽、井戸などの「地中埋設物」が残っていないかどうかも、あわせて確認します。見つかった場合には、埋設物を撤去するための工期が追加されます。
解体後に建物を建てる時や売却する時に、地中障害物があれば撤去費用が改めて発生してしまうため、解体時の撤去をおすすめします。
7.産業廃棄物の搬出
解体工事では、たくさんの廃材が生じます。産業廃棄物の処理は解体業者の義務なので、しっかりと分別して、それぞれの処理場へ運びます。近年は、分別処理のルールが厳しくなっていることもあり、産業廃棄物の処理費用が高く設定されていることも。安く済ませるためには、家具・家電などを自分で処分しておきましょう。
8.清掃と整地
最後に解体後の土地を平らにするために整備をします。
整備工程では専用の重機やトンボを用いて、デコボコの地面を踏み固め均します。
なお単に平らに整備する方法だけでなく、砂利を敷き詰める整地方法や、アスファルト舗装を依頼できるケースも。土地の利用が決まっている場合には、整備方法を解体業者と相談しておくと良いでしょう。
整備後には立入り禁止用の区画の杭とロープを設置し、道路や周辺のスペースの泥や砂埃などをきれいに清掃すれば完工です。
住宅解体後にやるべき手順

住宅解体では、工事が終わった後の手続きなども必要です。
工事前の準備同様に、忘れると罰金を科されたり、思わぬ請求がきたりすることもあるため注意しましょう。ここからは、解体工事後にやるべき手続きなどの手順を紹介します。
水道の停止
工事に使用した水道を止めましょう。水道は、その地域を管轄する水道局に連絡することで止められます。近年はインターネットで手続きできる水道局も多く、24時間いつでも申請できます。
使用停止手続きをしておかないと、水道を使っていなくても基本料金がかかることも。工事が終わったら早めに連絡しておきましょう。
近隣挨拶・事後調査
工事で迷惑をかけた近隣住民に、工事が完了したことを報告しましょう。カンタンに挨拶をしておくだけでも、関係性の悪化を防げます。
また、必要に応じて事後家屋調査を案内しましょう。工事後すぐに調査して事前調査の記録と比較することで、そのあとに「工事のせいだ」と言いがかりをつけられる心配がなくなります。
建物滅失登記申請
建物滅失登記とは、その土地の建物がなくなったことを国と自治体に報告する書類です。建物滅失登記は、解体工事後1か月以内に施主が提出する義務があります。怠ると10万円以下の罰金を科されるため、忘れないうちに提出しておきましょう。
また、建物滅失登記申請は、固定資産税の計算にも関わります。提出が遅くなると税金の計算がわかりにくくなってしまうので、早めに提出の準備をはじめましょう。
売却・建て替えなどの準備
解体後の更地を放置すると、雑草などによって荒れてしまいます。管理の手間が増えるだけでなく、近隣トラブルの原因になってしまうでしょう。そのため解体後はすぐに売却や建て替えの準備を進めるのがおすすめです。
解体後に建て替えない場合には、コンクリートやアスファルトで整地することも。建て替え・売却など、解体後の活用方法によって施工内容が異なります。
固定資産税は1月1日時点で計算されるため、12月31日までに売却が完了すれば、翌年の固定資産税を節約できます。
まとめ
住宅解体では、工事の前後に書類提出などの手続きが必要です。書類の作成には専門知識が必要なため、迷ってしまう方が多いでしょう。そのためまずは、解体工事の専門業者に相談するのがおすすめです。
複数業者の見積もりを依頼して、対応の丁寧さや見積もりの明確さを比較しましょう。専門業者と一緒に手続きを進めていくことで、はじめての方でも失敗せずに解体工事を終えられますよ。
株式会社上池解体興業(BOCCOS/ボッコス)では、現地調査と見積もり作成を無料で承っております。お客さまが抱える不安や疑問を解消し、安心して任せられる業者になれるよう、誠心誠意対応いたします。解体工事をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
千葉・埼玉・神奈川・東京の住宅解体
会社名:株式会社 上池解体興業(ボッコス/BOCCOS)
住所:〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-6-22
TEL:03-6846-5035
営業時間・定休日:9:00~18:00 日曜日